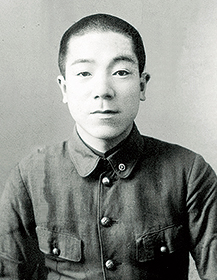- HOME >
- エピソード
エピソード Episode
エピソード1:船井哲良の少年時代~戦国武将伝、40歳で5つの会社の社長
「戦国武将伝」「立志伝」に学ぶ
船井哲良は、昭和2年(1927)、神戸市でミシン業を営む両親の下、4人兄弟の三男として生を受けた。
少年時代の船井は、ひとことで言えば腕白小僧だった。喧嘩もよくした。
そのような小学生時代、船井は4年生頃から、腕白な生活のかたわら古本の戦国武将伝に熱中しはじめた。ときには授業中に、教科書の内側に武将伝を挟んだまま、こっそり読みふけった。気づいた教師が父兄会で何度も親に注意をするほどだった。
古本に生き生きと描かれた、戦国時代の武将の生き方を通じて、船井は人間の生き方や、英雄のリーダーシップのあり方を学んでいった。まるで自分の物語のように、血湧き肉躍らせて血肉とした。学校の勉強には熱心ではなかった。学校の教科書のかわりに、戦国武将伝が「生きた教科書」となった。
旧制中学の神戸村野工業学校(現在の神戸村野工業高校)に入学した頃から、読書の対象は、戦国の武将伝から古今東西の起業家の立志伝へと変化した。限られた小遣いで少しでもたくさんの書籍が読みたくて、古本ばかりを買い求めた。当時「石炭箱」と呼ばれた大きな木箱があり、その2箱が一杯になった。冊数にして200冊は下らない量であった。食事の用意ができたと母親から呼ばれても「いま本を読んでいるので後にしてくれ」と言ったほど熱中してむさぼり読んだ。
武将や経営者たちの伝記から、「立身出世をする人間は、何か変わったことをしている。普通どおりにやっていたわけではない」と船井は気づいた。皆、裸一貫で勝負している。自分も同じように勝負したい!
戦国武将伝や経営者の立志伝を読んでいるうちに、いつしか船井の心の中に「夢、志」が膨らんでいったのである。
18歳、廃墟からのスタート
しかし、当時の日本は戦争中であった。船井は米軍が本土に上陸して来たら、相手が火炎放射器を振りかざす間隙を突いて、自分が死ぬだけでなく竹槍で相手も殺そうと覚悟していた。
昭和20年(1945)8月15日正午、疎開先で聞いた玉音放送によって終戦を知らされた。日本の大都市の多くは焼け野原となっていた。敗戦によって、日本人のほとんどが、今日の食事さえままならない貧しさの中に置かれたのである。
しかし、日本中が喪失感に沈むなか、生来の負けず嫌いが船井の中で燃え盛っていた。子どもの頃から戦国武将伝や東西の起業家の立志伝で学んだ「企業経営」の夢、志。
「皆、一斉にスタート台に立った。チャンスだ」
戦争とその終結によって、過去の財産や実績があってもそれは消えてしまった。文字通り、皆が一斉にゼロから新しいスタートを切ることになった。それならば、実力の勝負だ。
船井はある意味では幸運な世代であった。通常なら年齢から言って、戦争がさらに長引いていれば徴兵され戦地に行くはずだった。日本はすでに敗退に次ぐ敗退を重ねており、若い船井が徴兵されれば激戦地に赴いたに違いない。そうなれば、生きて帰れる可能性は高くなかった。しかし戦争が8月に終結したため、わずかの時間差で徴兵されなかった。そのため、船井は期せずして、最も若い年齢で戦後社会のスタートを切ることになったのである。
「敗戦で、日本は焦土と化している。しかし、自分のためにも、日本のためにも、このまま負けるものか。ゼロから商売を立ち上げてやる」という激しい闘志が船井の中にみなぎっていた。
疎開するまでは父親が神戸でミシンの卸を営んでおり、母が店頭でミシンの小売りの応対をしていた。日本にはこれから洋風の文化が流れ込んでくるだろう。今後、洋裁のミシンが入ってくれば、ミシンとともに洋裁が盛んになり、洋裁学校も経営できる。以前、父親の代わりに裁縫加工会社にリースしたミシンの集金に行ったことがあるが、あのような裁縫加工と、工業ミシンのリース会社もつくれる。卸、小売、洋裁学校、縫製加工、貸しミシン(工業用ミシンのリース)。
「よし、40歳で5つの会社の社長になる」
今に見ておれ、と18歳の船井は決意した。
エピソード2:荷造りで悟った「魂の入った仕事」
夢を追って強引に入社
起業を夢見た船井は、商売の基本を学ぶため、当時日本最大のミシン卸問屋であった大阪の東洋ミシン商会で修業しようと考えた。そのため、疎開先の徳島から大阪に出ることを決めたが、そこで意外な壁に直面したのである。
終戦直後の当時、地方から都市へは転入者の制限がなされていた。というのも、食糧事情が劣悪であったため、配給できる米が限られており、大都市への急激な人口流入を避けるためであった。
しかし、一刻も早く大阪に行き、東洋ミシン商会に入ってスパルタ教育を受け、商売で一人前にならねばならなかった。
ある日船井は、新聞で「鉄道要員募集。都市転入可」と書いてあるのを見つけた。国鉄大阪支局の求人広告だった。「これだ」と直感した。1年だけそこで働き、東洋ミシン商会に転職すれば良いと思いついたのだった。実際に応募してみると、相手方の手違いで寮がまだできておらず、自宅待機になってしまった。しかし、このまますごすごと徳島に帰るわけにはいかない。読みふけった戦国武将伝や偉人伝では、立身出世をした人は普通の決まり通りにやってきたのではない。何か飛び抜けたことをしている。
そこで船井は、国鉄の総務課長に「大阪市内の親類の家から通う」と言って、大阪市への都市転入証明書を出してもらったのである。
その足で、転入証明書片手に東洋ミシン商会を訪ねた。
そして総務課長に「私を採用してほしい。住み込みで働く」と頼んだ。しかし、総務課長は「国鉄職員の転入証明書だから、国鉄に行かなければ話がおかしい」と首をかしげた。もちろんそれが正論である。
しかし、船井は「国鉄に行かないのは自分の都合だから会社には迷惑をかけない。もし問題が起きたとき、国鉄に怒られるのは私自身だ」と強引に東洋ミシン商会に入社してしまった。
「40歳で5つの会社の社長になる」という夢と志が、船井を強引なまでの入社に突き動かしたのであった。
そして、船井の人生の道は確かにそこから開け始めたのである。
「そんな仕事は、やめとけ」
東洋ミシン商会は超スパルタ教育で知られていた。「3日勤めたらどこの会社でも勤まる。3か月勤めたら、どこの会社に行っても幹部(当時は番頭)になれる。3年勤めたら自分で商売できる」と言われていた。
仕事の厳しさに耐えかねて、せっかく入社したものの、辞めてしまう店員が絶えなかった。そのため船井がいた4年のあいだ「見習店員、住み込み店員募集」の貼り紙がはがされることなく貼られていた。
寮に入ったものの、先輩たちは船井に名前を聞いてくれさえしない。不思議に思って尋ねてみると、「どうせすぐに辞めてしまうから」という返事だった。
社長の武藤鍬三郎氏は明治生まれで、旧制の夜間商業学校しかでていない。16歳のときに当時世界最大のミシンメーカーでアメリカに本社を置くシンガーミシンの横浜支店に給仕見習いで入社し、最終的には日本地域を統括する総支配人にまで上り詰めた。大正4年に40歳で独立、一代で東洋ミシン商会を大きくした。戦争で負けて昭和22年に財産税を取られたとき、大阪国税局管内で6、7番目に大きな額を支払ったという成功者であった。
入社してすぐの仕事は、ミシンの頭部を入れた木箱を荒縄で縛る荷造り作業だった。工業学校時代から立身出世した偉人伝を大量に読んでいた船井は、それら偉人が普通の人よりもはるかに努力していることを知っていた。そのエピソードに倣い、人が夕方5時に仕事を終えても、6時、7時と常に2時間余分に仕事をした。そうすれば、社長は必ず自分を認めるだろうと読んだのである。早く荷造りの仕事を卒業して、営業に出たかった。というのは、当時ならではの事情があった。
当時は戦争直後で食糧事情がきわめて劣悪であった。米穀類の配給が2合3勺しかない。これだけでは栄養失調になってしまう。そのため毎日午前10時と午後3時には近所の喫茶店に行って芋を食べて空腹をしのぐ。給料はみんな食事代で消えてしまった。しかし、営業に変わると地方に出ることができる。地方へ行けば、白米、海の幸、山の幸がたらふく食べられたのであった。夜行列車に乗って旅館代を浮かし、その金で新しい服を買うこともできたのである。
空腹に耐え荷造りをしていると、狙いどおり、残業している船井の仕事振りを武藤社長が見に来た。社長が近づくと、ちょっと甲高い独特の靴音でそれがわかった。社長から「ご苦労さん。夜遅くまで仕事してるな。もう、いい加減にやめろ」というお褒めの言葉がかかるはずだった。しかし、そうではなかった。遅くまで一人で働いている船井に、武藤社長はただ一言、「そんな仕事は、やめとけ」としか言わなかった。
船井は意地になり、あくる日も遅くまで残業していた。するとまた社長がやってきて、それもやめとけと言ってまったく相手にしない。
「本で読んだ古今東西の偉人と違って、この社長は仕事というものを何もわかっていないな」と船井は思った。
後から後から荷造りの仕事が出てくる。木箱を縛る荒縄で手の皮がむけ、血がにじんだ。早くその仕事から脱出したかった。早く営業に出してもらうため、激しい空腹と戦いながら船井は懸命に働き続けた。
荷造りコンテストで一番になってみせる
そんな日々が1か月ほど続いたときだった。営業に出た先輩が帰ってきて、船井の荷造りを手伝った。その先輩は、驚異的なスピードで次々と荷造りをこなしていった。船井の3倍ものスピードだ。
なぜだ! 自分は体力には人一倍自信がある。それにもかかわらず、先輩の仕事に負けている。空腹に耐えながら、人よりも長い時間懸命にやっている。根性も持ちあわせている人間が、なぜ負けるのか。
そうか、結局、今の仕事は要領だけでやっている……。
私の仕事には魂が入っていなかった。
そのことに気がついた。船井は悟り、改心した。荷造りコンテストで一番になってみせる。当時、船井のような新人を集めて荷造りのコンテストが行なわれていた。そのコンテストで絶対に一番になってみせる。日本一になってみせる。
それ以来、船井は荷造りコンテストのまさに本番真っ只中という思いで、わき目もふらずに荷造りに集中した。社長の靴音が近づいてきても気がつかないほど作業に魂を入れるようになった。
3か月ほど経ったある日、武藤社長が船井の肩をポンポンと叩いた。そして「おい、お前、これから営業や」と言った。
あまりに荷造りに精魂をこめていた船井は、目標どおり荷造りコンテストで一番になってから行きます、と言いかけたが、かろうじてその言葉をのみこんだ。せっかく得たチャンスを活かすべきだと思った。
この体験を通じて、船井は、仕事に魂が入っているかどうか、ということの大切さを身をもって学んだ。「心頭滅却すれば火もまた涼し」という言葉があるが、それほどに一心不乱に仕事をすることで、その仕事は本物になる。生産性が向上する。真に生産性を上げるには、魂の入った仕事をすることだ。
その真理を、このとき身をもって学んだのであった。
エピソード3:不渡手形という大失敗に学ぶ
独立半年で巨額の不渡手形をつかむ
船井もこれまで数多くの失敗を経験してきたが、その中でも最大の失敗であり、人生でもっとも辛かった経験といえるのが、この出来事であった。
武藤社長が引退したこともあって、昭和26年(1951)6月に独立、個人商店「船井ミシン商会」を設立した。ミシン完成品、及び部品の卸問屋で、船井も入れて4名。当時24歳だった。
その年の12月、船井はとんでもない失敗をおかすこととなった。当時の売上げ約6か月分に相当する巨額の不渡手形をつかまされたのだ。
月商わずか20万円のときに、その6倍となる120万円の負債。当時は弁護士資格を持っている人の初任給がだいたい1万円。120万円の借金を払おうと思ったら、毎月飲まず食わずでも10年はかかる金額であった。
輸出用ミシンの完成品メーカーに部品を納入する仕事だった。その話は、東洋ミシン商会のかつての上司から持ちかけられた。その先輩は退社後、ミシン業界でブローカーをしており、そのメーカーからの注文を受け、これを船井の店で受けてほしいと持ちかけてきた。船井は先輩を信用して商品を卸し、代金を手形で受け取った。
ところが、それが銀行の帳簿に載らない、いわゆる「簿外手形」だったのである。商品の納入、手形の受け取りはその先輩を通じて行なっていたため、メーカーについて自分では十分調べていなかった。
その受取手形が簿外手形であることが、支払期日である12月31日の1か月前に、取引相手のメーカーから通知されてわかった。
そのまま手形を3か月ジャンプ(支払期日の延期)すれば、銀行帳簿に載せることができた。しかし、仕入先への支払いを守ることを考えれば、期日どおりに手形を現金化したい。ところが、簿外手形ということは決済に回すと不渡りとなる可能性が高いのである。仕入先への信用を落としても一度ジャンプするか、あるいは不渡り覚悟で手形を決済してみるか。船井は血尿が出るほど1か月間悩みぬいた。
そして意を決して年末に手形を取引銀行に入れたところ、まさに不渡りとなってしまったのであった。
卸問屋であったから、たくさんの納入業者がいた。彼らが皆、債権者となった。なんとしても彼らに支払いをしなければならない。
意を決した船井は、支払期日当日の12月31日、大晦日、納入業者の中でも特に信頼関係の厚かった7、8人の業者を集めて、一緒に不渡手形を出したその輸出メーカーを訪ね、この手形をどうしてくれるのかと詰め寄った。
相手方メーカーも役員会を開いて対応を協議した。この結果、倉庫にあった輸出前の完成ミシンを手形と同じ金額分、引き渡すということで決着がついた。昼の3時頃から始まった交渉が、夜の7時であったか、8時であったか、ようやくまとまったのであった。
しかし大晦日の夜である。ミシンを運ぼうにもトラック会社はすでに閉まっている。一番場所が近い債権者のところに小型トラックでピストン輸送し、終わったのは元旦の午前零時半を過ぎていた。しかし手に入れたミシンを売れば、金は回収できる。納入業者たちにも支払ができる。かろうじて危機を乗り越えられたのであった。
この経験が船井を大きく成長させた。
輸出に舵を切るという閃き
元日の深夜1時半に帰宅し、午前3時頃床に入った。目を覚ますとすでに夕方5時となっていた。さっきまでのことが走馬燈のように浮かぶ。なんとか忘れたい。船井はパチンコ屋の喧騒の中で夜10時まで過ごした。翌日の2日も何も手につかず、朝10時から夜10時までパチンコをして過ごした。3日目も同じようにパチンコ屋の喧騒の中で張り詰めた気持ちを癒した。
40歳で5つの会社の社長になるはずの自分が、立志伝に描かれた人物たちのようになるはずだった自分が、わずか半年で倒産寸前に陥った。なぜだ。なぜなのだ……。なぜこのような失敗を……。
そして、ある重大な発見をした。
今後の進路を大きく変える発見だった。
不渡手形を振り出したミシンメーカーの取引実態をよく調べて見ると、輸出貿易ではあらかじめ「信用状(L/C)」という銀行保証がつくことがわかった。信用状とは、貿易決済を円滑化するための手段として銀行が発行する支払い確約書であり、輸出者は船積みと同時に輸出代金を回収することができる。つまり、100パーセント間違いなく代金が回収できるのである。
まてよ、と船井は閃いた。輸出に舵を切ったらどうか。
当時はまだ戦後の混乱期で、商売上の道徳も乱れていた。国内では、また不渡手形をつかむ心配があった。しかし、輸出なら信用状によって代金が100パーセント、しかも事前に回収できるのである。
船井はすぐに輸出貿易について猛勉強を始め、国内でのミシン卸売に加え、海外へのミシン輸出業務も始めることにした。
不渡手形をつかむという一世一代の大失敗から、輸出事業というまったく新たな道がひらけたのである。
世界を相手に、グローバルにビジネスを行なう船井電機の第一歩が、まさに生涯最大の失敗から始まったのであった。
そして一方で、120万円の借金から逃げずに対応した誠意ある行動が口コミで次第に広がり、大阪のミシン業界内に知れ渡っていった。信用はお金に替えられない。その大切な信用、いったん失いかけた信用が、むしろいっそう高まったのであった。
エピソード4:プレミアの浮利を捨て、新たな挑戦へ
「毎月2000万円」のプレミアを捨てて
現在で言えば、毎月2000万円が、何もしなくても入ってきた。
まだ30歳になるかならないかであった。
「これでいいのか。何かがおかしい。何もせずにお金だけ入るが、ほんとうにこれでいいのか」
船井は何度も自問自答した。そして、
「40歳で5つの会社の社長になるという夢はどうなるのか!」
その強烈な思いが、船井に決心をさせた。
「ミシンに代わって何か新しいことをやろう」
若き経営者となった船井は、仕事に熱中し、得意先を走り回っていた。戦後の復興需要の中で、昭和20年代後半、船井は順調に日本製ミシンを海外に輸出し続けた。
ところが転機が訪れる。アメリカ向けの安値ミシンの輸出が大量に行なわれたため、貿易摩擦が起こったのだ。
その結果、政府の指示によりアメリカに配慮して生産調整が行なわれるようになった(「クオータ制」)。昭和29年末より全国を3地区に分け、「日本輸出ミシン調整組合」が設立された。船井は大阪支部の理事に就任した。まだ28歳の若さであった。
クオータ制が導入されると、各メーカーでは一定数以上の生産ができないため、各々の生産枠に対してプレミアが生じる結果となった。たとえば100の生産枠しか与えられていないメーカーに110の注文が入ると、そのメーカーは他社から不足分の生産枠10を「購入」しようとする。ここに「プレミア」が生じた。
当時のミシン業者は、この生産枠を他者に売る(プレミア)だけでもかなり利益となったのである。
昭和30年から33年にかけて、船井はこのプレミア分だけで、毎月100万円近い収入を上げていた。大卒の初任給が1万円の時代。100万円といえば、現在で言えば2000万円ぐらいとなる。それが黙っていても毎月入ってきたのであった。
トランジスターラジオという「夢」
「同じ輸出でも、まだ規制のないトランジスターラジオをやってみたい」
日本経済は、昭和30年から高度成長期に入っていた。
輸出用トランジスターラジオの生産は、まさに時代の転換期と重なり合い、ピタリとタイミングが合っていた。
もちろんそれは、結果が出て振り返るから言えることであり、時代の渦中にいた船井には、そこまでの未来は読みきれなかった。もし誰の目にも成功が明らかであれば、誰でも始めるし、大企業のほうが圧倒的に有利である。船井も「ミシンは一度買ったら一生ものだが、ラジオはプラスチックでできている。落としたら壊れるからまた買う。ラジオなら注文がいくらでもある。先行きは明るいのではないか」という未来予測をするのが精一杯だった。
しかし、船井には夢と志があった。夢と志が、「幸運の女神の前髪」をしっかりとつかませてくれたのだった。
まだ1台も生産していないにもかかわらず、船井はミシンの会社の中に新たにトランジスターラジオ部門を加えた。
そして「株式会社船井ミシン商会」の名前まで、「船井軽機工業株式会社」と変更してしまった。軽機とは今では使わない言葉だが、軽機械の略である。ミシン部門とラジオ部門の二頭立てだが、ミシンの名前を社名から外してしまったのであった。
しかし、ミシンからトランジスターラジオへの業種転換には、数々の「壁」が行く手に立ちはだかっていた。
エピソード5:5時間の交渉
一歩も動かぬ執念
とうとう前金を受け取り、領収書を渡してくれた。
根負けしたのか、それとも熱意を多少は認めてくれたのか。
すでに5時間が経っていた。船井は粘りに粘って、そこを一歩も動こうとしなかった。相手がOKしてくれるまで粘り続ける覚悟だった。
ミシンの世界からトランジスターラジオで電機業界に入ったとき、絶対に必要だったのがトランジスターとバリコン(可変コンデンサー)だ。だが、これらを供給できるメーカーはごく限られており、なかなか思うようには入手できなかった。トランジスターラジオ用のバリコンはミツミ電機しか作っておらず、日本の生産量は事実上ここで決められていた。バリコンがなかったらラジオが作れない。
船井はそのラジオ用のバリコンを独占的に製造していたミツミ電機に、部品を分けてもらうために乗り込んだ。だが、応対に出た営業課長の森部一夫氏(後にミツミ電機社長)は、実績がない船井など相手にしてくれない。早く帰れと言わんばかりである。ミツミ電機としても、既存の得意先からの受注をこなすので精一杯の忙しさだった。
船井は部品の前金を手に、一歩も動こうとしなかった。東洋ミシン商会の店番頭時代、粘り強く何時間も動こうとしないお客と商談し続けた経験がある。そのときに学んだことを活かしたのだった。まずは野球のような柔らかい話でうちとける。相手が少し心をひらいたら商談に入る。商談が難航したら、次は相撲の話……、押したり引いたり。
時間が経つと、やはり相手もだんだん親身になってくる。まだラジオを一度も製造していない船井が語るのは「夢」しかない。「我々は将来、月産10万台のラジオを作る会社になる。バリコンも大量に仕入れるようになるから、何とか売ってほしい」と執念で頼み込んだ。夢を実現するためには、どうしてもバリコンが必要だった。
森部課長はとうとう、根負けしたように500個分の前金を受け取り、領収書をくれたのである。前金を申し出たのは、絶対に部品を渡してもらうための保証であり、継続して部品を出してもらうための保証でもあった。
領収書をもらったら、船井はさっそく社員をミツミ電機に毎日行かせて催促した。「お金は払っているから、商品をいくらか出してくれ」。そこまでしなければ供給を確保できない物不足の時代であった。
こうして船井はバリコンをミツミ電機から供給してもらえることになり、大阪の今里に設けた工場で昭和34年(1959)5月トランジスターラジオの生産を開始した。記念すべき第1号となったのは6石1 バンド(AM)のトランジスターラジオであった。
エピソード6:時代の風に乗る-船井電機のスタート
沖縄からのラジオ輸出という「奇策」
今里工場でのトランジスターラジオの生産は順調で製品輸出も好調だった。もちろんこれは船井軽機工業だけの話ではない。他の大手家電メーカーもトランジスターラジオの量産に取り組んでいたため、日本国内での生産は過剰になってきた。しかもそのほとんどはアメリカに輸出されていた。
このような状況が続く中で、最大のマーケットであるアメリカでは日本製トランジスターラジオの輸入阻止運動が起こった。このことを受け、通産省(当時)は対米輸出を規制する狙いからミシンと同じくトランジスターラジオにも「クオータ制」を導入した。船井が今里工場で生産を開始した翌年の昭和35年(1960)4月のことである。生産を始めたばかりで実績がない船井軽機工業には、生産枠がほとんど認められない。好調な滑り出しを見せたかに思えたトランジスターラジオ事業は、いきなり大きな壁に突き当たってしまったのである。
そんな時、船井にあるアイデアがひらめく。沖縄でトランジスターラジオを生産し、そこからアメリカへ輸出するという「奇策」である。
当時の沖縄はアメリカの統治下にあって日本の施政権がおよばない地域だった。そうであるならば、通産省の規制外であり、「クオータ制」も適用されない。
現地に飛んだ船井はその場で契約を交わし、現地の食品会社と、商社との3社合弁で「琉球軽機工業株式会社」を設立した。そして食料品の工場を電気製品の工場に作り変え、沖縄でトランジスターラジオの製造を開始したのである。クオータ制の施行からわずか4か月後のことであった。
沖縄からの輸出なら出荷制限を受けることはない。こうしてトランジスターラジオはこれまで通りアメリカに向けて大量に輸出された。
「船井電機株式会社」の誕生
ミシンからトランジスターラジオへの業種転換は見事に成功した。トランジスターラジオの生産は急拡大し、船井がミツミ電機の森部氏に語った「月産10万台」の夢は、わずか数年で実現したのである。
昭和36年(1961)8月9日、船井は船井軽機工業からトランジスターラジオ部門を分離独立させて「船井電機株式会社」を設立し、今里工場に本社を置いた。これは名実ともに家電製品分野に進出するという宣言であるとともに、今日へと続く船井電機の歴史がスタートした瞬間であった。
エピソード7:「FPS」最強の生産システムの誕生
魂を入れて働く姿
背水の陣だった。
「もし脱落するならば、会社を退職いたします」という退職届を出したうえで行ってもらった。
昭和52年に行なった幹部社員100名による、3か月間に及ぶ実地研修。場所はトヨタのグループ企業の日野自動車羽村工場。
現在の船井電機の強さを、具体的な仕組み、生産体制として支えているのが「FPS(フナイ・プロダクション・システム)」である。研修は、そのFPSが誕生する瞬間となった。
あるコンサルタントの紹介で、船井はトヨタ車の製造現場、羽村工場を見学する機会を得た。受付を済ませて工場内に入った瞬間、緊張感あふれるピンと張り詰めた空気、気迫と集中力、真剣に仕事に取り組む従業員の姿が船井の目を奪った。
それは、船井自身が東洋ミシン商会で学んだ、魂を入れて荷造りに取り組む姿とまったく同じであった。
「今の時代にまだこんなに働く会社があるのか」と、船井は呟いていた。全員が命がけで、100パーセントのエネルギーを出して働いている。すさまじい生産性の高さを実現していることが一目でわかった。
これを船井電機の幹部社員全員に体験させ、魂を入れて集中して働くことの大切さを自覚させなければならない。そしてそれは、社員一人一人の人間的な向上においても、大切な経験であり大きな財産となるだろう。
折から、日本経済には「円高」という強烈な試練が襲いかかっていた。それを乗り越えることができるのか。船井は強い危機感とともに毎日を過ごしていた。幹部社員に研修で実体験をさせ、学んだことを船井電機に導入し、急激な円高にも負けない高度の生産性を実現しなければならない。
100名の、しかも精鋭を出すのだから、企業としてはたいへんな負担になる。しかし、なんとしてもやらなければならない。トップダウンの決断であった。
人間の能力は無限だ
研修は過酷なものとなった。電気製品であればともかく、自動車製造は初めてであったから、実地研修を受けた者たちの手は翌日には動かなくなるほどだった。仕事が終わって飲むビールの栓が抜けない。手の平から血が出て、固まって、また血が出て固まる。しかし、それを繰り返していく中で、手がだんだんと硬くなる。そうやって3か月も経てば、少々のことではこたえなくなる。
昼休みにはバレーボールやキャッチボールをしている人がたくさんいるというのに、研修に行った者たちは1か月ほどは死ぬほど辛く、グッタリとして彼らの姿を見ることしかできなかったという。しかし、3か月目には、当初3人分の仕事ではないかと思っていた作業が簡単にできるようになったのである。
幹部社員は、人間の能力は無限だということを身をもって学んでくれたのであった。そして、能力を高めようと思えば110パーセント、120パーセントの負荷をかけること、魂を入れて真剣に取り組めば生産性が飛躍的に向上することを、自家薬籠中の物として学んでくれたのであった。
船井電機の幹部社員が研修で学んだことに、さらに独自の工夫を加えて出来上がったのが「FPS」なのである。
一方で船井は、昭和44年(1969)から50年にかけて、大阪工業大学の故・竹山増次郎教授の研究室と、どうすれば企業の生産性が上昇するかという産学協同の調査研究を6年間も行なっていた。そのような学術的なアプローチもあわせて進めていたことも、FPS成立の土台となった。
船井は研修の効果を確かめるため、毎週早朝、大阪から岡山県津山市の工場に通った。現場では、朝8時にボタンを押すと全員が戦車のように一斉に動くようになっていた。「これなら船井電機は円高の危機を乗り越えることができる」と、現場が自らの姿を通して船井に教えていた。生産ラインは見違えるように生まれ変わっていた。そして、これからもますます向上することをはっきりと予感させてくれたのであった。


 青年期の船井哲良(右から3人目)
青年期の船井哲良(右から3人目)